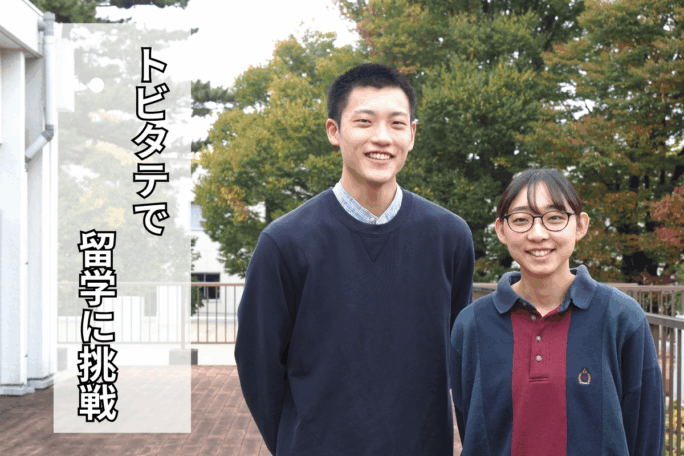今年2月に千葉大学の主催でオンラインワークショップ「Japan-ASEAN Online Program toward SDGs 2024」が行われました。このワークショップにはASEAN諸国と国立六大学*の学生57名が参加し、お互いの文化や社会的背景に対する理解を深めながら、「環境」という全世界に共通する課題に対して白熱した議論が展開されました。
参加者の母語はさまざまであるため、英語を使って議論し意見をまとめるという難しいワークショップでしたが、「参加して得たものはとても大きかった」と語ってくれた国際教養学部4年・大島三和さんと常田千尋さんにお話を伺いました。
*千葉大学、金沢大学、新潟大学、岡山大学、長崎大学、熊本大学の六大学

普段接することのない海外の学生との交流に参加を決意
――本日はよろしくお願いします。まずは今回参加されたプログラムの内容について教えてください。
大島さん(以下、敬称略):ASEAN大学連合と日本の国立六大学連携コンソーシアムが交流し、ともに学ぶ取り組みが10年以上にわたって行われているのですが、今回のワークショップはその一環として開催されたものとなります。
今回のテーマは「環境のために学生が起こすことのできるアクション」で、合計57名の学生が9つのグループに分かれてSDGsの目標達成に向けたディスカッションやプレゼンテーションを行いました。
――お二人が参加したきっかけは何ですか?
常田さん(以下、敬称略):私は以前カンボジアに1年間留学していて、帰国後その興味の範囲がASEANに広がっていきました。今回はさまざまなバックグラウンドを持つ学生と話ができることに興味を持って参加することにしました。
大島:私は以前タイに行ったことがあるのですが、その頃のタイは大気汚染がひどく、医療用のマスクをしなければならない状況でした。「これが同じ地球なんだ」と驚くとともに、環境問題は特定の地域に限定したものではないということを肌で感じた経験があったので、海外の学生と同じ目的を持って議論できる場としてぜひ参加したいと考えました。

――今回のワークショップはディスカッション形式で行われましたが、これまでもそのような経験はあったのですか?
常田:私たちの所属している国際教養学部は座学だけでなく、アクティブラーニングを取り入れている授業がとても多いので、全くの未経験ではありませんでした。
大島:ただ、全て英語でのワークショップはあまり経験がなかったです。グループメンバーは全員バックグラウンドが異なるというかなりハードルの高い環境だったので(笑)、参加前はちょっと緊張していました。
社会的・文化的バックグラウンドもさまざま。英語を使ってのグループディスカッションに四苦八苦

――それぞれグループで設定したテーマと、決めた理由について教えてください。
大島:私たちのグループは、まず参加者それぞれが関心のある環境問題を出し合ったのですが、水に対する課題意識を皆が持っていたので、比較的スムーズに「海洋汚染」というテーマに落ち着きました。
常田:私たちはそれぞれの国・地域で社会的な問題となっていることを洗い出しながら、共通して言えることは何かを議論し、「ゴミ処理問題」をテーマにしました。
――どのように議論を進めていきましたか?
常田:進行役は、私が務めました。初めはみんな積極的な雰囲気だったので、「みんなで議論を引っ張ってくれるんじゃないかな?」と期待して臨んだところ、意外にもなかなか意見が出てこなくて…。
自分なりに役割を果たそうと、それぞれの名前を呼んで意見をもらうとともに、できるだけ共感した点や疑問に感じた点などを意識して話すようにしました。その甲斐もあってか、徐々に周囲からも自然と意見が出てくるようになり、終盤はかなり活発な議論を行うことができました。
大島:私たちは比較的に最初から意見も出ていました。今回は「大学生ができること」というテーマだったことから、日頃から慣れ親しんでいるSNSを活用して意識啓発をしていこうという方向性になり、YouTubeやインスタグラムでどのように発信していくかという具体的な話し合いになっていきました。
ただ、議論が進んでいくなかで、一人のメンバーから「自分たちは学生だからこそ、もっとアカデミックな解決策を模索すべきだ」という意見が出たんです。まとまりかけているところだったので「えっ?」という空気も流れましたが(笑)、それもそうだよねということで、途中からガラッと方針を変えて考えることになりました。

――進行役としては大変でしたね(笑)。
大島:はい(笑)。ただ、そこからは化学や物理などそれぞれが持っている知識を出し合いながらアイデアを検討していきました。ただでさえ、それぞれの母語でない言語を使っているのに、さらに専門用語まで出てくるのでとても難しかったです。
でも言葉だけでなく、図なども活用しながら「相手に伝える」スキルを学ぶことができましたし、それぞれが大学で学んでいる知識を活用して一つの解決方法にまとめていくという過程はとても有意義なものになりました。
――常田さんはいかがでしたか?
常田:ある国では不法投棄が大きな問題になっていたり、日本ではある程度システムがしっかりしているがゆえに問題に対する関心そのものが高くないという課題があったりと、一言に「ゴミ処理問題」といっても、国によって状況が大きく異なります。その目線を合わせるのがとても大変でした。
ただ、色々と議論をする中で、処理が難しい「プラスチックのゴミを減らすこと」は共通の課題なのではという結論に達し、これを解決する方法を皆で考えました。
「国・地域」という枠組みを超えて、「人と人」の交流を意識することが重要

――最終日に発表した解決方法と、他のグループからのフィードバックがあれば教えてください。
大島:私たちがまとめたのは、ドローンやフィルターを活用した海洋ゴミの回収システムです。回収したゴミを化学的に処理し、環境負荷を低減する方法まで説明し、共同研究や資金面でのサポートについては企業と連携していくことを提案しました。
アカデミックな視点からの解決策を提案したため、斬新なアイデアだと評価していただいた一方、「学生ができる範囲を超えているのでは?」という意見もいただきました。
常田: 私たちは、「捨てられたプラスチックを使って何ができるか?」というテーマで同世代に向けてワークショップを開くというアイデアだったのですが、「自分たちにもできそう」という評価をいただくことができました。また、導入部分で各国のゴミ問題の現状をデータとして紹介した部分については「国ごとの状況は知らなかった」「一個人としてやれることがあるかもしれない」など、とても多くのコメントをいただき、関心を集められたことはとても嬉しかったです。
――ありがとうございます。それでは最後に、プログラム全体を通して、印象に残ったことや学んだことについて教えてください。

大島:さまざまなバックグラウンドの学生と交流し、議論したことによって、私が思いつきもしていなかったようなことを深く考えていたり、実際にアクションを起こしたりといった参加者の熱意を感じることができたのは本当に刺激的でした。
今回の機会はより良い社会を作るために自分に何ができるかということを考えるきっかけになりましたし、考えるだけではなく行動を起こせる人間になっていきたいと感じました。
常田:背景が異なる人たちが集まって一つのテーマについて話す難しさも、逆にそれが実現した時のすばらしさも感じることができました。日本はある程度生活水準が安定していますが、進学率が10%にも満たない国・地域もあります。彼らのリアルな生活や取り巻く環境を考えるきっかけを得られました。
また国際関係を考えるとき、今までは漠然と「国・地域」という枠組みで考えていましたが、やっぱり「人と人」が交流することで作り上げられていくんだということを気づかせてもらった良い機会となりました。私は日本で生まれましたが、そのアイデンティティを大切にしながら、これからも多くの国・地域の人と交流の場を積極的に作っていきたいです。
最後に、本プログラムを担当された国際未来教育基幹の岡山先生からもコメントをいただきました。

環境に関するSDGsの目標を軸に、学生たちが自分たちの視点からアクションを考える——そんなワークショップに、12か国から約60名の学生が参加してくれました。
国・地域によって異なる価値観や文化背景、環境に対する問題意識を持つメンバーがオンラインで議論を深める中で、欠かせなかったのが千葉大学の学生たちの存在です。英語力と積極性を兼ね備えた10名の学生が各グループのファシリテーターを務め、議論をリードし、まとめ上げてくれました。彼らの尽力があったからこそ、最終日のプレゼンテーションは質の高いものとなり、多くの海外参加者からも高い評価を得ることができました。
学生たちの力が国際的な舞台で生きる瞬間を目の当たりにし、教育の現場としての大学の可能性をあらためて感じています。今後もこうした取り組みが広がり、多様な価値観をつなぎながら、持続可能な未来を築く一歩になればと願っています。
大島さん、常田さん、そして岡山先生、ありがとうございました。お二人の所属している国際教養学部もぜひチェックしてみてください。
国際教養学部HPはこちら