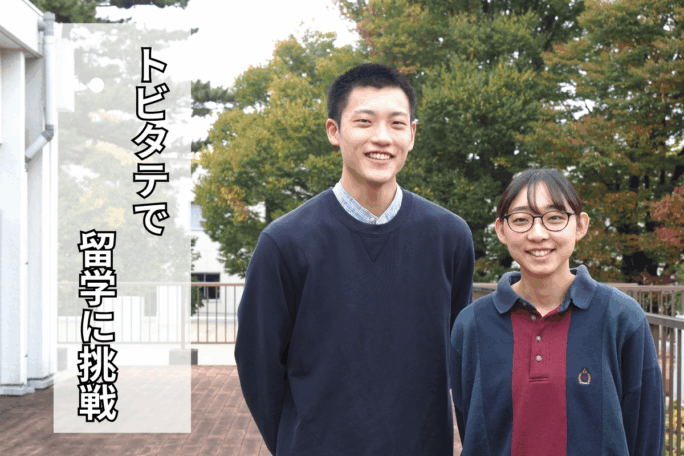鉄棒にぶら下がり、ロープをよじ登って障害物を駆け抜ける――。ダイナミックな動きでスピードと技術を競う「オブスタクル(障害物)スポーツ」は、まだ日本では数百人ほどしか競技者がいませんが、2028年のロサンゼルスオリンピックでは近代五種の1つとして採用され、今注目されているスポーツです。この競技で大活躍しているのが、千葉大学国際教養学部1年生の山本遼平さんです。今年9月に行われたスウェーデンで開催された世界大会では、強豪選手を相手にジュニア部門3位入賞という快挙を達成しました。
大学生活との両立を図りながら、「競技者」としてだけでなく「普及の担い手」としても活動を広げる山本さん。新しいスポーツを切り拓く先駆者としての挑戦についてお話を伺いました。

挑戦の原点は「遊び」の延長
――オブスタクルスポーツを始めたきっかけを教えてください。
山本さん(以下、敬称略):オブスタクルスポーツを明確に「競技」として意識したのはごく最近で、初めて大会に出場したのは2年半ほど前のことです。
振り返ると、幼い頃から体を動かすことが好きで、父が休日のたびにアスレチック施設に連れて行ってくれるのが楽しみでした。丸太を渡ったり、ロープをよじ登ったりと、最初は純粋に「楽しいからやる」という感覚でした。そんな遊びの中で、大人でも苦労するような遊具を軽々とこなせる自分に気づいたとき、「もっと挑戦したい」という思いが芽生えたのだと思います。

――小中学校ではほかのスポーツに打ち込むことはなかったのですか。
山本:小学校高学年のときは陸上部に所属していたのですが、中学校では部活動に入らず、代わりに近くのパルクール*施設に通っていました。そこで出会う人たちは宙返りなど派手な技を見せる中、自分はそうした動きが得意ではなく、全然できませんでした。ただ、鉄棒での飛び移りやバランス感覚を必要とする動作は自然とできる。自分の身体の特徴や得意分野が確かにあると感じ、それが今の競技に直結しています。「遊びで身についた感覚がそのまま競技の基盤になっている」――そう思うと、子どもの頃の体験は大きな意味があったと感じています。
*パルクール:フランス生まれの、走る・跳ぶ・登るなどの「移動動作」で心身を鍛える運動方法。街や森で、自由にスタートとゴールを決めて、障害物を越えることで体を鍛えていくスポーツ。(日本パルクール協会より引用)

父と一緒に作り上げた「手づくり練習場」
――普段はどんな環境で練習しているのでしょうか。
山本:千葉市内にある自分専用の練習場で取り組んでいます。「オブスタクルスポーツ」という言葉をまだ聞いたこともなかった2019年頃に、父と二人で資材を集め、一から組み立てて作りました。専門業者に依頼したのはほんの一部だけで、大半は手作業。設計図があるわけでもなく、海外の映像や写真を参考に見よう見まねでの挑戦でした(笑) 強度を確保するために分厚い鉄パイプを使い、壊れやすい木材は避けるなど、試行錯誤を繰り返しながら形にしていきました。現在では、関東圏の選手が集まる練習拠点にもなっています。

――個人で施設を作る…?大変ではありませんでしたか?
山本:実は、競技人口の多い米国では約800カ所のジムがあるのですが、それもプロの業者ではなく、選手たちが自ら作っているケースが多いのです。それを見て「自分たちにもできる」と思えたことが大きな励みになりました。
父は競技の経験者ではありませんが、子どもの挑戦を応援したいという思いから常に協力的で、資材探しや設計の工夫、強度の確認までいつも一緒に取り組んでくれました。今では日本代表団のコーチとして海外大会に帯同するほど。自分にとっては競技者としての挑戦を支える存在であると同時に、オブスタクルスポーツを日本に広めていく活動を共に進めるパートナーでもあります。
世界大会ジュニア3位、そして見えた課題
――スウェーデンでの世界大会に出場していかがでしたか?
山本:出場したのは「OCR100m*」という短距離の障害物競技です。この大会は、予選を勝ち上がった16名の選手でトーナメント戦を行う形式だったため、40分ほどの間に最大で4本走らなければなりませんでした。通常、日本の大会では3本を1日がかりで行うため、連続で走り続けるこの方式は想像以上に過酷でした。
最初の2本を走り抜けた段階で体力は限界に近づき、準決勝ではわずかなミスが響いて敗退。それでも気持ちを切り替え、3位決定戦では渾身の力を振り絞って勝ち切り、銅メダルを手にすることができました。表彰台に立ったときの達成感は大きかった一方で、「さらに上に行くには何が必要か」という課題も鮮明になった大会でした。 海外の選手は身体能力の高さに加え、未知の障害にも即座に対応できる柔軟さを持っています。本大会のコースは日本の練習環境とは大きく異なり、ジュニアでも屈強な選手がいるという層の厚さを実感しました。
※100メートルに11の障害物が置かれ、より速いタイムを出すことで競う。


――オブスタクルスポーツの現状や展望について、山本さんはどう感じていますか。
山本:日本での競技人口はまだ数百人規模にとどまっており、認知度も低いのが現状です。一方、世界では「Ninja」と呼ばれる競技を含めると数千万人が関わっているとされ、欧米やアジアでは大会も盛んに行われています。この差は練習環境や大会数だけでなく、競技が「文化」として根付いているかどうかにも表れていると感じています。
日本でも2023年に「一般社団法人日本オブスタクルスポーツ協会(JOSA)」が設立され、本格的に普及・拡大に向けた活動が始まっています。今回の私の銅メダル獲得がきっかけとなり挑戦する人が少しずつ増えていけば、環境も整い、競技全体が成長していく。先駆者としての責任を感じながら、自分自身もさらなるレベルアップを目指したいと思っています。
学業と競技の両立、そして未来へ

――千葉大学に進学した理由を教えてください。
山本:千葉大学を選んだ理由のひとつは、「グローバル」という視点です。スポーツで世界を目指したいという気持ちは強いですが、競技だけに打ち込み「学生としての自分」をおろそかにしてしまうと、将来このスポーツを広める際に説得力を欠くと思っています。自分の背中を見て育つかもしれない次の世代に、「競技と学業は両立できる」と示すことも、先駆者としての大切な役割だと感じています。
千葉大学の国際教養学部の幅広い学びができる環境にも惹かれました。高校も国際教養科に在籍していたのですが、スポーツ以外に打ち込みたいものがまだ見つかっていなかったこともあり、国際教養学部は「自分の考え方や興味が変わっても対応できる」柔軟さがあると感じられたので、進学の決め手になりました。
――普段の生活はどのように過ごしているのですか。
山本:基本的には週2回の本格的な練習と、週3回の軽めのトレーニングを組み合わせています。激しい練習では練習場で全身を使って障害を越える動きを繰り返し、軽めの日は体幹トレーニングや懸垂、指先の強化など、地味ですが必要な基礎を積み重ねています。 授業期間中は、遠征先にも必ずパソコンを持参し、移動や空き時間を使って課題をこなしています。アジア圏内の大会であれば、大会を終えた日の夜に飛行機へ飛び乗り、帰国することもありました。
生活の中で最も重視しているのは睡眠で、1日平均10時間を目安に休むようにしています。しっかり眠ることで体が回復し、集中力も維持できる。睡眠を確保することが、トレーニングや学びの質を高める一番の近道だと思っています。
――それでは最後に、今後の目標を教えてください。

山本:今の一番の夢は、オリンピックの舞台に立ち、メダルを獲得することです。また、オブスタクルスポーツを将来的にはオリンピックの単独種目として定着させたいと考えています。そのためにはまず、自分が国際大会で安定して成績を残し、存在感を示す必要があります。
同時に、普及活動にも力を注いでいきたいと思っています。子どもから大人まで多くの人に体験してもらうことで、このスポーツの魅力を広めたい。「遊びの延長からでも世界を目指せる」という自分自身の経験を通して、挑戦するきっかけを提供したいのです。特別な才能がなくても、体を動かす楽しさから始められる――その入り口を伝えることが、自分の使命だと思っています。
山本さん、貴重なお話をありがとうございました。
山本さんが在籍される国際教養学部ウェブサイトはこちらをご覧ください
オブスタクルスポーツ世界大会での銅メダル獲得についてのニュースはこちら