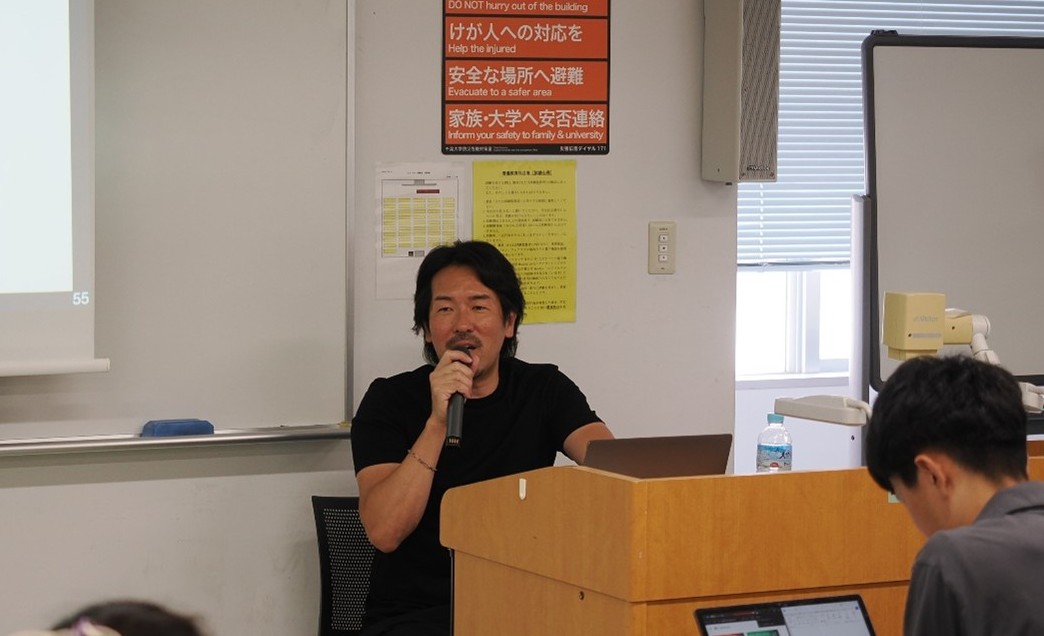
昨シーズン悲願のB1昇格を果たしたプロバスケットボールクラブ「アルティーリ千葉」(以下、アルティーリ)。レギュラーシーズンの勝率9割越えという圧倒的な強さを発揮した同チームですが、「勝つだけがプロスポーツの存在価値ではない」とし、千葉大学が連携協定のもとに展開しているのが、実践型の連携授業です。この授業は単なるスポーツと教育のコラボレーションにとどまらず、学生が「生きたビジネス」の現場に触れ、地域とのつながりを学ぶ機会として注目を集めています。
果たしてこの取り組みは学生にどんな気づきを与え、大学や地域にどのような価値を生み出しているのでしょうか?今回は株式会社アルティーリ代表取締役CEO・新居佳英氏と、連携授業を担当している千葉大学教育学部の下永田修二教授にお話をお伺いしました。
勝つことが全てではない。ビジネスとしてプロスポーツを運営することとは?
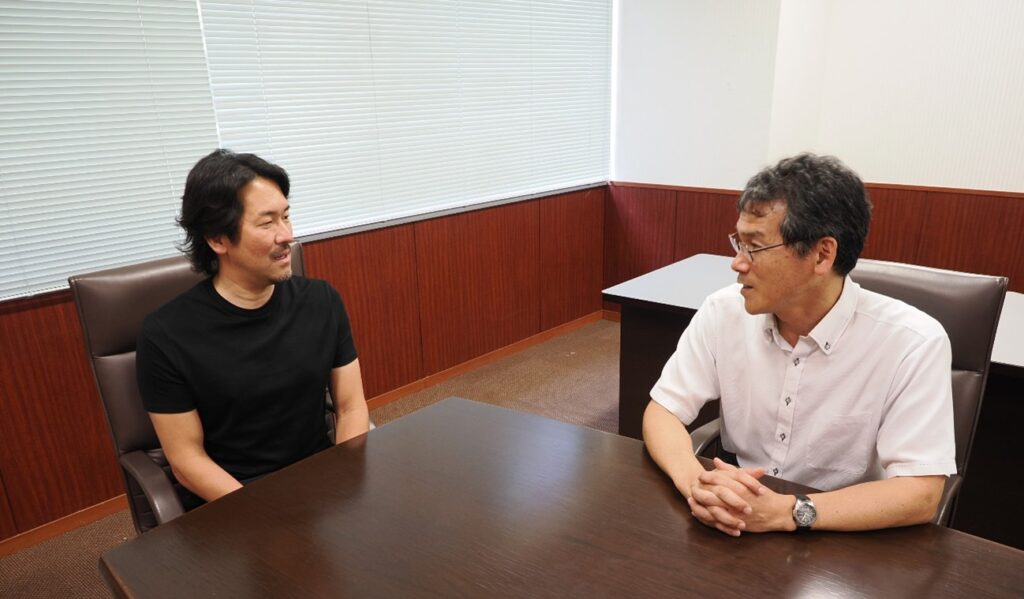
――B1昇格おめでとうございます!まずはアルティーリ千葉というクラブの特徴や設立の背景について教えてください。
新居様(以下、敬称略):ありがとうございます。アルティーリ千葉はBリーグ参入を目指して2020年に千葉市をホームタウンとして設立された、まだ若いプロバスケットボールクラブです。設立初年度でB3からB2への昇格を果たし、続く2年目・3年目もB2東地区優勝を達成しました。しかし、いずれもプレーオフのセミファイナルで敗退し、あと一歩のところで涙を呑みました。そして迎えた昨シーズン、ついに悲願のB1昇格を果たすことができました。
こうして振り返ると順調にステップアップしているように見えるかもしれませんが、決して平坦な道のりではありませんでした。さまざまな困難に直面しながらも、多くの方々の支えや応援があって、ここまでたどり着くことができたと感じています。
もちろん、プロスポーツクラブである以上、勝敗にこだわるのは当然です。ただ、私たちはそれだけにとどまらず、地域社会とともに歩み、千葉市に根ざした価値を提供できる存在でありたいと考えています。
――なぜそこまで地域貢献を重視されているのでしょうか?
新居:プロスポーツは「勝てばそれでいい」というものではありません。選手やクラブスタッフだけでなく、ファンやスポンサー、行政、そして地域に暮らす方々など、多くのステークホルダーの支えによって初めて成り立つビジネスです。
今後、新たなアリーナの建設を予定していますが、このプロジェクトもまた、千葉県や千葉市といった行政の皆さまのご理解とご協力により実現に向かっています。
そうした地域社会の方々の支えに対して、私たちは“勝利”という成果だけではなく、もっと広い意味で価値を還元していきたいと考えています。たとえば、地域経済の活性化や、子どもたちの健やかな成長を支える場づくりなど、クラブの存在そのものが地域の未来にポジティブな影響をもたらす。そんな役割を果たすことが、私たちアルティーリ千葉の大きな使命であり、目指すべき姿だと思っています。
千葉大学との連携授業、その狙いと効果とは

――連携授業を始めた背景についてお聞かせください。
下永田先生(以下敬称略):学校の体育では、「する(実際に体を動かす)」「みる(観戦する)」「支える(運営やサポートに関わる)」「知る(背景や仕組みを理解する)」という4つの視点が重視されています。このうち、「する」や「みる」は授業の中でも比較的取り組みやすいのですが、「支える」についてはなかなか実践の場がないのが現状です。だからこそ、プロスポーツクラブの運営やその裏側に触れる機会は、学生にとって非常に貴重な学びになると考えました。
以前より医学部付属病院とアルティーリ千葉との人材交流が始まっていたこともあり、2024年にスポーツと教育の発展を通じて地域振興を目指す連携協定を締結しました。今回の連携授業は、その取り組みの一環としてご協力をお願いしたかたちになります。このうち、「する」や「みる」は授業の中でも比較的取り組みやすいのですが、「支える」についてはなかなか実践の場がないのが現状です。だからこそ、プロスポーツクラブの運営やその裏側に触れる機会は、学生にとって非常に貴重な学びになると考えました。

――授業の内容や、工夫しているポイントなどについても教えてください。
新居:登壇するのはクラブスタッフだけでなく、Bリーグ関係者など、現場の第一線で活躍している方々にも協力していただいています。多様な立場からのリアルな視点を届けることで、学生にとってより立体的で実践的な学びになることを目指しています。
この連携授業は今年で2年目になりますが、内容をアップデートしながら運営しており、とくに学生との“対話の時間”を大切にしています。たとえば、「どうやってファンを増やすのか?」というテーマで、実際のマーケティング施策や戦略について講義した回もありました。これは、単に理論を教えるのではなく、私たちが直面しているリアルな課題を素材に、学生と一緒に考える機会をつくるという意図があります。
――授業を通じて、学生にどのようなメッセージを伝えたいとお考えですか?
新居:プロスポーツクラブというと、どうしても“強いか弱いか”だけで評価されがちですが、その裏側には明確なビジョンや戦略、そして多くの人々の協力によって成り立つビジネスの営みがあります。そうした側面を知ることで、学生たちがビジネスや社会に対して具体的な関心を持つきっかけになってくれたらうれしいですね。
クラブが授業を通じて伝えたいことは、「ビジネスはおもしろい」ということ。社会に出ることや仕事をすることに対して、漠然と“厳しいもの”というイメージを持っている学生も多いかもしれません。でも、夢や目的を持って働くことは、時にとても楽しく、やりがいに満ちたものです。そんな“大人の本気”や“働くことの楽しさ”をリアルに感じてもらうことが、何よりのメッセージになると信じています。就職活動という枠にとどまらず、人生の選択肢として「仕事ってワクワクするものなんだ」と思ってもらえたら嬉しいです。
――実際、学生の反応はいかがでしたか?
下永田:まさにそのメッセージがしっかりと学生たちに届いていて、授業では目を輝かせながら真剣に話を聞く姿がとても印象的でした。将来の選択肢を広げる機会になったと、私自身も確信しています。
授業後の感想では「理念に強く共感した」「社長の情熱が伝わってきた」「働くことが楽しそうだと思えた」といった声が多く寄せられました。知識だけでなく、物事に向き合う姿勢や考え方を学ぶきっかけになったと思います。ある学生は、授業後に「自分も起業を考えているのですが、どうすればよいですか?」と担当講師に直接相談しに行ったほどです。
新居:そうした学生の前向きな姿勢や積極的な質問の数々には、私たちも本当に励まされました。スポーツクラブの“裏側”にある現実を知ってもらうことで、ビジネスや社会に対する関心が高まり、将来への視野が少しでも広がってくれたなら、それだけでこの授業には大きな意味があったと思っています。 私も学生からのアンケートに目を通しましたが、クラブが伝えたかった思いがしっかりと届いていたことを実感できました。これからも、こうした機会を大切にしていきたいですね。

これからの展望と学生への期待
――今後、千葉大学との取り組みをどのように発展させたいとお考えですか?
新居:授業に加えて、学生がボランティアやインターンとして参加できる機会をもっと増やしていきたいと思っています。実際の仕事現場に触れることで、クラブが大切にしている価値観や姿勢を“肌で感じてもらう”ことができるはずです。イベントや試合の運営をサポートしてもらう際には、単なる作業ではなく、学生が責任を持って役割を担えるような機会を意識して設計していきたいですね。
下永田:教室での学びを“実践”につなげることは、教育上とても重要です。インターン制度の活用や大学祭とのコラボイベント、大学の体育館を活用した子ども向けイベントの開催などを通じて、アルティーリ千葉・千葉大学・地域の三者が有機的につながるような取り組みを目指していきたいと考えています。実際、学生からは「試合運営のスタッフを1日体験してみたい」といった声も上がっており、今後の展開に大きな可能性を感じています。
――ありがとうございます。最後に、それぞれ今後の抱負をお聞かせください。
新居:B1昇格は私たちにとって、新たなスタートラインです。これから始まるBプレミア(2026年から始まる日本の男子プロバスケットボールリーグの新しいトップカテゴリー)での優勝、そして日本を代表するチームへと成長していくことを目指します。一方で繰り返しになりますが、ただ“強いチーム”になるのではなく、地域にエネルギーをもたらす存在であり続けることが私たちの理想です。その過程を通して、学生たちにも「夢」と「現実」の接点に触れてもらい、一緒に歩んでいけたらと思っています。
下永田:アルティーリ千葉との連携が、地域スポーツと教育をつなぐ新しいモデルケースとして広がっていくことを期待しています。学生の成長を支えながら、地域に貢献し、共に未来を描いていける関係をこれからも築いていきたいですね。いつか、学生たちと一緒にアルティーリ千葉のBプレミア優勝の瞬間を迎えられる日を、心から楽しみにしています。



